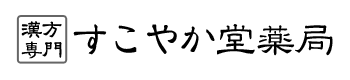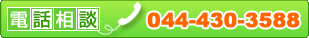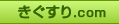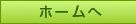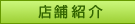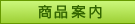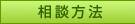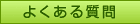~お知らせ~
誠に申し訳ございませんが、
7/16(火)は、お休みいたします。
7/14(日)15(月)16(火)と連休になります。
どうぞよろしくお願い致します。
すこやか堂薬局
| ツイート |
|
更新日: 2024/07/05 |
|
<不妊症の漢方>
日本では10組に1組が不妊症と言われています。漢方では、身体のバランスを整え(陰陽の調和をとり、ホルモンのバランスを整える)、血の汚れをとり、血の流れを改善することで妊娠しやすい状態にしていきます。また、精子減少症、無力症など男性が原因の場合も40%あると言われています。男性の不妊症には腎系の働きを改善する薬を使い、精子の数、運動を高めていきます。 《不妊症、生理不順》 不妊症に悩む人の多くは、生理不順を伴う場合が非常に多いものです。生理不順を治すことで、不妊が改善する場合があります。西洋医学では、女性不妊を卵巣、卵管、子宮、骨盤腹膜に器質的異常があるものを器質的不妊といい、原因がはっきりしないものを機能性不妊といいます。また、原因が男性にある場合もあります。 《不妊症、生理不順の代表的な漢方薬》 ● 当帰芍薬散・・・貧血ぎみで、冷え性、疲れやすい人が目標です。 帯下などがしばしばあり、膀胱炎をおこしやすいタイプの人で、 圧迫されるような鈍痛の生理痛がある人に用います。 ● 桂枝茯苓丸・・・・体力は普通であざができやすく、顔はのぼせて 手足が冷えるといったいわゆる冷えのぼせタイプで唇や舌の色は 赤黒い人が目標です。 ● 加味逍遙散・・・・足が冷えて顔がのぼせ、肩こり、頭痛、めまい、 不安感、イライラなどの神経症状強くあらわれる人に用います。 ● 補中益気湯・・・・手足の倦怠感があり、疲労しやすく、消化器系が弱く、 体力のない人に用います。男性不妊の、精子のきが悪い人にも用います。 ● 婦人宝 [第2類医薬品] 〔シロップ剤〕 (1) 「女性の宝」と重用されている「当帰」が、処方の約7割を占めます。 (当帰1日配合量5.52g) (2) 中医学では、女性の「健康と美容」は「血液の健康」と密接な かかわりがあると考えます。 婦人宝は、気血を補う生薬が、多数配合されてますので 「血虚」の方に最適です。 (3) 血の巡りを良くし、血の量を豊かにして、体全体の機能を高め、 冷え症・貧血など女性特有の諸症状に優れた効果を発揮します。 (4) 甘くて飲み易い「シロップ剤」です。 《不妊症、生理不順によいと言われている民間薬、機能性食品》 サフラン、トウキ、コウカ、シャクヤク、ヤクモソウ、ホオズキの黒焼き粉末 <注意> 漢方薬は、お一人お一人の体質や病気の状態合わせて処方されるオーダメイドのお薬です。 体質が違えば同じ病気、同じ症状でも飲む漢方薬が違ってきます。 お飲みになる場合は必ず漢方の専門家にご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2024/07/03 |
|
《梅雨~夏にかけて増える、「気象病」梅雨だる、 頭痛・めまい・倦怠感、神経痛・胃腸障害》
気象病とは、天気の変化が影響して身体や精神に起こるさまざまな不調のことで、特に梅雨時~ジメジメして暑い夏にかけて多くみられるようです。 天気の変化や台風接近などにより気圧が下がると、自律神経のバランスが崩れ、血管が拡張し、神経に影響を与え、気象病を引き起こすと考えられています。 気象病は、天候の変化が影響して起こる不調の総称であるため、症状も多岐にわたります。 頭痛、片頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、神経痛、肩こり、喘息の悪化、不眠、気分の落ち込み、さらに抑うつなどの精神的な症状が起こりやすいと言われています。 気象病の原因 漢方では、気圧や気温の変化で悪化する場合、「水毒」が関わっていると考えます。体の中の水分バランスが乱れ、頭重感(頭がダル重い)、むくみ、痛み、吐き気、めまい、耳鳴りなどの症状を引き起こします。「水毒」を改善するには、水分代謝をよくする漢方を中心に使います。 (気象病(水毒)による症状を改善する代表的な漢方薬) 頭痛・・・五苓散 めまい・・・苓桂朮甘湯 神経痛・・・薏苡仁湯 胃腸障害・・・六君子湯 倦怠感・・・・補中益気湯 一人一人の体質が違うので、ご自身の体質に合った漢方薬を服用することが大切です。 ★すこやか堂では、一人一人の症状や体質が多彩なため時間を掛けてお話を伺いその方に一番良い漢方薬をお選びおつくり致しております。 |
| ツイート |
|
更新日: 2024/06/29 |
|
めまいには、天井や周囲の景色がぐるぐる回るような感じがする回転性のめまい、立ち上がったときに起こる立ちくらみ、からだがふらふらするいわゆるふらつき、ふわふわする浮動感などさまざまなものがあります。
そのうち回転性のものを真性のめまいといい、それ以外のものを仮性のめまいといいます。 また、めまいがいつおこるかという不安感、恐怖感が精神的にも負担になってきます。 (真性のめまい) めまいの原因で一番多いのは、耳の内耳の三半規管には、リンパ液と、リンパ液の流れを感知する感覚毛があります。頭も動かすと、リンパ液が動いて体のバランスを感知しますが、ストレス、過労、睡眠不足、肩こりなどで、リンパ液の量が増えて、内耳がむくむことで、感覚毛に異常刺激が起き、平衡機能が正常に働かなくなりめまいが起こると言われています。 ①良性発作性頭位めまい症~頭を動かしたり、寝返りをうった時などめまいがします。三半規管の耳石器の機能異常が原因と言われています。 ②メニエール病~、内耳の中にある、液体の貯留(内リンパ腫)、回転性のめまいを繰り返し、めまい以外に耳鳴り難聴を伴うこともあります。 ③突発性難聴、原因不明、内耳のウイルス感染や血流障害ではないかと言われています。突然の難聴、回転性のめまい (仮性のめまい) めまいの原因は、様々で、(脳梗塞、脳出血等)早期に医師の治療が必要な疾患もあるため注意が必要です。頭痛、しびれ、麻痺伴う場合、スムーズに話せない、物が二重に見える、うまく歩けないのなどは、速やかに医師の診察を受けてください 漢方では、水毒やお血が気の上昇とともに起こると考え、柴胡加竜骨牡蠣湯や苓桂朮甘湯など気や水のめぐりをよくする漢方薬を使います。 仮性めまいの原因は、多岐にわたり高血圧、低血圧、動脈硬化、アレルギー、眼科疾患、更年期障害などがあります。また原因がわからないことも少なくありません。 更年期によるめまいは、動悸、のぼせ、発汗、不安等も併発する事が多く加味逍遙散や、柴胡桂枝乾姜湯などが使われます。 胃腸が弱く胃酸が出やすい方に多いめまいは、胃内の水毒がめまいを起こす考え半夏白朮天麻黄湯を使います。 高血圧症に伴うめまいには、釣藤散や抑肝散などを、低血圧に伴うめまいなどは、当帰芍薬散などを使います。いずれも血流を改善していくものを使います。 日常生活で気をつけることは、水分の取りすぎに注意し、塩分を控えめにして、後頭部を冷やさない様にして下さい。 すこやか堂では、一人一人の症状や体質を詳しくお伺いし、その方に一番良い漢方薬をお選びおつくり致しております。是非ご相談下さい。 |
| ツイート |
|
更新日: 2024/05/07 |
|
●田七人参(田三七人参)
田七人参(でんしちにんじん)はウコギ科多年生草本で栽培は難しく漢方で古来より使われてきた薬用人参の1種で、採取してから3年~7年後にやっと収穫できるため三七と呼ばれている。葉は薬用の人参に似ているから参三七とも言い普通には田七または田七人参といいます。またお金に換えられない程の価値があるという意味で、しばしば不換金(ふかんきん)とも呼ばれてきました。 田七人参は、約500年前の中国の文献にて「血液循環を良くし、痛みを止め、内蔵の出血を止める」として紹介されていた、無類の上薬だったそうです。(上薬とは「長く飲んでも副作用がない、穏やかな作用の漢方薬」を意味しています。)当時は一般の人が手に入れることが出来ない無類の上薬でした。 ▼ 一般に知られるようになったのは、ベトナム戦争の兵士が、止血薬として携帯していると報道された事からだそうです。古くから田七は、「止血の要薬」と知られていました。その後中国で、狭心症治療に用いられるようになり、心臓、動脈硬化、肝機能などの改善に役立つことが明らかになってきました。 <田七人参の効能>田七人参に代表される有効成分は、サポニンです。高麗人参にも含まれていますが、田七人参には高麗人参の約7倍のサポニンが含まれています。サポニンは血液に直接働きかけて、毒素を排出し、血液をキレイにしてくれます。血液がキレイになると、負担が軽くなった肝臓は元気を取り戻し、さらに血液循環を良くするという好循環がもたらされます。 また、田七人参の有効成分は、それだけではありません、他の種類の人参をはるかにしのぐ有効成分が数多く含まれています。具体的には、フラボノイド、ステロール、有機ゲルマニウム、鉄分、カルシウムなどのミネラル類、ビタミン、脂肪、タンパク質などがあります。 サポニンは、血液から筋肉への糖の取り込み量を増加させて、高血糖を抑制する作用があることが発見されています。食後の血糖値だけでなく、空腹時血糖値にも効果があるそうです。糖尿病を患っている方にとっても、非常に強力な効能があることがわかります。田七人参の最大の効能は、血液をキレイにして免疫力を高めることです。糖尿病や高血圧、痛風、高脂血症、婦人病、更年期障害、貧血など様々な疾病に効果があるとされています。 ◆こんな方におすすめです。 ・血流の悪い方、出血しやすい方 ・健康診断でいろいろな数値結果に不安な方・健康や体力の衰えを感じ始めてきた方疲れやすい方 ・心臓、肝臓、動脈硬化が気になる方 ・婦人科系疾患、生理不順、生理痛、更年期など気になる方 ・お酒を飲んだ翌日がつらい方、食生活が乱れがちな方・動悸・息切れが激しい方、糖尿が気になる方 etc... ・太り過ぎがきになる方 肝機能を高める効果 田七人参には肝細胞を再生する働きがあり、アルコールが原因で引き起こされる肝機能の低下にも効果が期待されています。 免疫力を高める効果 田七人参には抗ウイルス作用があります。人間には体内に侵入してきた異物を攻撃し、その異物を体外に排出したりする免疫機能が備わっています。ウイルスの増殖を抑え、ウイルスを破壊する効果があります。 生活習慣病の予防・改善効果 生活習慣病は中性脂肪、コレステロールの蓄積や活性酸素による体のサビつきなどが原因。田七人参は、血中の中性脂肪やコレステロールを分解、吸収を妨げる働きがあり活性酸素を抑制する効果もあります。血中の中性脂肪やコレステロールの吸収を阻害し、活性酸素を抑制する働きから、生活習慣病の予防・改善効果が期待できます。 血糖値を下げる効果 血糖値を下げる効果があります。筋肉での糖の取り込みを増加させ、筋肉での糖代謝を改善する効果があり、血糖値を下げる効果につながります。 血流を改善する効果 田七人参には、血流を改善する効果があります。血中の悪玉コレステロールの増加、老化や運動不足によって体の代謝機能が低下すると、体内に老廃物が蓄積します。そこで、血液ドロドロ状態になってしまうのです。田七人参は、血液のドロドロの原因となる中性脂肪やコレステロールを分解し、血流を改善するので次のような効果があります。 ■血糖値を抑制 ■血液をサラサラに ■心臓の機能を高める ■肝機能を活性化 ■慢性的な疲労を改善 ■ホルモンバランスを保つ ■免疫力を高める ■ダイエットに効く 《田七人参と不妊症》 田七人参は「血液に関するあらゆる不調」を整える効果があります。 子宮筋腫の改善 田七人参は、血行を良くして血の滞りを改善するため、子宮筋腫を小さくする効果があります。子宮筋腫の予防と解決は不妊治療に欠かせません。 生理痛の緩和 不妊症の女性に多く共通するのが生理痛です。田七人参は、血流の促進とホルモンバランスを整える効果があるため、子宮の状態を健康にし、経血をスムーズにします。これによって生理痛が緩和する効果があります。 冷え性の改善 田七人参は、血液の循環を良くする効能があるため、冷え性の改善が期待できます。血行促進によって体温が上がることで、子宮や卵巣の働きが活発になり不妊症に効果があります。 ■田七人参の副作用 重大な副作用はありませんが、以下のような症状が出た場合は注意しましょう。 経血などの出血量が増加する 田七人参は、血液の循環を活発にする効果があるため、体質に合わない人が服用したり、過剰摂取によって経血がひどくなる副作用があります。 胃痛や吐き気 胃腸の弱い人が服用すると、胃痛や吐き気の副作用があります。 |
| ツイート |
|
更新日: 2024/04/10 |