人の体は清濁を併せ持つ存在ですが、
この事を漢方の世界では、 陰陽 として表現します。
陰陽とは東洋医学の基本となる重要な考え方で、
大変に奥の深いものですが、簡単に言えば
人の体が培っているものには 二面性がある ということです。
人の体には清濁のみならず、老若や剛柔など数多くの二面性が共存しています。
また自律神経(交感神経と副交感神経)や
性ホルモン(男性ホルモン、女性ホルモン)など、
人の体に備わる機能や分泌物も二面性を持っています。
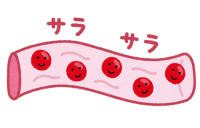
体を流れる血液にも、実は二面性が備わっています。
例えば、集まろうとする凝集性と広がろうとする拡散性もそれです。
血液の状態を「ドロドロ」とか「サラサラ」とか言い表しますが、
あれこそまさに二面性をうまく表現しています。
ドロドロは少し病的なイメージが強いですが、
極端に陽に偏ってドロドロしていない。
かといって陰に偏って水っぽくてサラサラしすぎていない。
それが、全身を隅々まで巡ることができる血液の条件です。
なお前者を赤い血、後者を青い血と呼ぶとか呼ばないとか・・・。

この事を漢方の世界では、 陰陽 として表現します。
陰陽とは東洋医学の基本となる重要な考え方で、
大変に奥の深いものですが、簡単に言えば
人の体が培っているものには 二面性がある ということです。
人の体には清濁のみならず、老若や剛柔など数多くの二面性が共存しています。
また自律神経(交感神経と副交感神経)や
性ホルモン(男性ホルモン、女性ホルモン)など、
人の体に備わる機能や分泌物も二面性を持っています。
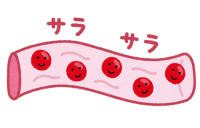
例えば、集まろうとする凝集性と広がろうとする拡散性もそれです。
血液の状態を「ドロドロ」とか「サラサラ」とか言い表しますが、
あれこそまさに二面性をうまく表現しています。
ドロドロは少し病的なイメージが強いですが、
極端に陽に偏ってドロドロしていない。
かといって陰に偏って水っぽくてサラサラしすぎていない。
それが、全身を隅々まで巡ることができる血液の条件です。
なお前者を赤い血、後者を青い血と呼ぶとか呼ばないとか・・・。

血液の陰陽のバランスが陽に偏れば、その血液によって養われる他の部分、
例えば内臓や肌、分泌物、場合によっては精神面なども次第に陽に傾いたりします。
陰陽のバランスは、それが良いものであれ悪いものであれ、
からだの他の部分に伝わったり、影響を与えていきます。
例えば内臓や肌、分泌物、場合によっては精神面なども次第に陽に傾いたりします。
陰陽のバランスは、それが良いものであれ悪いものであれ、
からだの他の部分に伝わったり、影響を与えていきます。
もっとも陰陽というのは、陰が良いとか陽が悪いとかそういう尺度ではありません。
陰(あるいは陽)に大きく偏っている状態 、それが心身の健康に良くない訳です。
漢方における予防は、この陰陽のバランスを保つことに通じており、
崩れたバランスを元に戻すことが治療に当たります。
もっとも、「陽に傾いたからといって、陰を高めれば良いか?」といえば
実際はそう単純でない点に漢方治療の妙があります。
陰(あるいは陽)に大きく偏っている状態 、それが心身の健康に良くない訳です。
漢方における予防は、この陰陽のバランスを保つことに通じており、
崩れたバランスを元に戻すことが治療に当たります。
もっとも、「陽に傾いたからといって、陰を高めれば良いか?」といえば
実際はそう単純でない点に漢方治療の妙があります。

















