季節外れの暑さを感じるかと思えば、暑さはまた鳴りを潜め、
あれやあれやと夜には肌寒さを感じるようになりました。
ここの最近の、暑さの変動には目を見張るものがあります。
暑い日が続くと、体の気血の巡りは盛んになり、
暑さに応じた体調になっていきます。
体が暑さを覚える、暑さに慣れるとはこの事を言うのだと思います。
けれどその狭間で、ふいに暑さが静まると、
盛んになった気血は行き場を失い、迷走します。
「暑くないのだから、引っ込んでおれ!」とはなりません。
自律神経による、ある程度のコントロールは可能でしょうが、
今まで暑さに応じた神経を、突然の肌寒さに対応させるというのは、
日本の公道運転に慣れている人間が、
アメリカ式の公道運転の訓練の最中に、
「すまんが今日は、日本式で走ってくれ!」と催促されるような話です。
そこで混乱が起きるのは当然ですが、今までの
癖のようなものが出現する点にも、注意が必要です。
それまでの気血の状態を引きずってしまう。
季節の変わり目にかぜを引きやすくなるというのは、
何となくわかる、経験があると思いますが、その多くは
温かさの急落(温かさの狭間の肌寒さ)に伴うものだと考えられます。
「温かさに慣れた一種のデメリット」とでも言いましょうか?
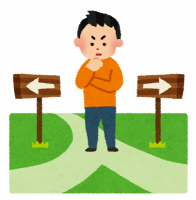
あれやあれやと夜には肌寒さを感じるようになりました。
ここの最近の、暑さの変動には目を見張るものがあります。
暑い日が続くと、体の気血の巡りは盛んになり、
暑さに応じた体調になっていきます。
体が暑さを覚える、暑さに慣れるとはこの事を言うのだと思います。
けれどその狭間で、ふいに暑さが静まると、
盛んになった気血は行き場を失い、迷走します。
「暑くないのだから、引っ込んでおれ!」とはなりません。
自律神経による、ある程度のコントロールは可能でしょうが、
今まで暑さに応じた神経を、突然の肌寒さに対応させるというのは、
日本の公道運転に慣れている人間が、
アメリカ式の公道運転の訓練の最中に、
「すまんが今日は、日本式で走ってくれ!」と催促されるような話です。
そこで混乱が起きるのは当然ですが、今までの
癖のようなものが出現する点にも、注意が必要です。
それまでの気血の状態を引きずってしまう。
季節の変わり目にかぜを引きやすくなるというのは、
何となくわかる、経験があると思いますが、その多くは
温かさの急落(温かさの狭間の肌寒さ)に伴うものだと考えられます。
「温かさに慣れた一種のデメリット」とでも言いましょうか?
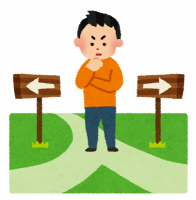
漢方では、春は「陽長陰消の過渡期」と言われますが、
煽(おだ)てられた陽の勢いは、急には止みません。
そんな「陽」の手綱を握るのは・・・、
「陽中の陰」と称される肺か、はたまた「陰中の陽」の肝か。
イメージの話ですが、エンジンの回転数が上がっていく自動車を制御するのに、
トラクションを増やす、ダウンフォースを稼ぐというテクニックがあるように、
回転数が上がる陽の勢いにも、同じことが言えるのではないでしょうか?
「暑さの狭間の肌寒さ」に服んでおきたい漢方薬とは即ち、
温かさ・暑さで盛んになっていく気血の巡りの脇を固める漢方薬を意味します。
それには例えば、桂枝加黄耆湯や防已黄耆湯、苓桂朮甘湯、
あるいは柴胡桂枝湯や逍遙散などに一服の価値があるかと思います。
煽(おだ)てられた陽の勢いは、急には止みません。
そんな「陽」の手綱を握るのは・・・、
「陽中の陰」と称される肺か、はたまた「陰中の陽」の肝か。
イメージの話ですが、エンジンの回転数が上がっていく自動車を制御するのに、
トラクションを増やす、ダウンフォースを稼ぐというテクニックがあるように、
回転数が上がる陽の勢いにも、同じことが言えるのではないでしょうか?
「暑さの狭間の肌寒さ」に服んでおきたい漢方薬とは即ち、
温かさ・暑さで盛んになっていく気血の巡りの脇を固める漢方薬を意味します。
それには例えば、桂枝加黄耆湯や防已黄耆湯、苓桂朮甘湯、
あるいは柴胡桂枝湯や逍遙散などに一服の価値があるかと思います。

















