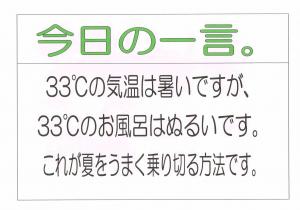人の体温は一年を通してだいたい36℃です。この36℃が保たれている理由は簡単に言えば『代謝』です。外から食べ物を取り入れて、消化・吸収、その過程で熱を発生するという仕組みも持つからです。この仕組みがない変温動物、例えば爬虫類は、外気温が低いとそれに影響されて自身の体温も低下して、まともに動けなくなります。脳みそも働かなくなります。だから俗に言う『ひなたぼっこ』をして、体温を上げる必要があります。
ちなみに生きている限り熱は常に発生し続けます。昼夜を問わず。では発生した熱はどこにいくか。体の外に発散します。そうしないと、体に熱が溜まってしまい、オーバーヒートしてしまいます。
» 続きを読む
夏に暑いと感じる理由は、この熱の発散がうまくいかないからです。一つには、気温が高いほど熱を発散しにくくなります。熱は暑いものから冷たいものに伝わるので、体温と外気温が同じだと、熱は行き場を失くします。
もう一つには、空気自体が温まりにくく、冷めにくいという性質を持っています。水は空気に比べて1000倍も温まりやすく、冷めやすいです。同じ33℃の大気とお湯で、大気を暑いと感じるのは、人の体から大気に熱が発散されていかないから。お湯を熱いと感じないのは、人の体から発散された熱が水にどんどん吸収されていくからです。
いかにして熱を発散していくか。熱を発散しにくい季節≒夏だといえます。
熱を発散させやすくするためには
①自分の周囲の気温をいかに下げるか=冷房機器で空気を冷やす
②自分の周囲に発散した熱をいかに効率よく吸収させるか=肌を水分と接する(汗とか濡れタオル)
の二択になります。