昔も今も、日々の健康維持や増進に必要なのは
冷え(冷食)と気苦労(ストレス)への備え。
すなわち、「温める事」と「気血を巡らす事」。
この二つを併せ持つのが、他ならぬ薬用人参というわけです。
温める事と、気血を巡らせる事。
おのおのの効能に秀でた素材というのは数多くありますが、
二つの効能を兼ねたものは数少ない。
例えば、温める効能をもつものには、
薬用人参の他にも生姜や大蒜(にんにく)が挙げられますが、
ではこれらに、気血を巡らせる働きがあるかと言われれば・・・。
たしかに、温めることでからだの働きが上がり、巡りも良くなります。
ですがそもそも、からだのどういう部分が温まるのでしょうか。
といいますのも、生姜や大蒜はいずれも辛味。
辛味を摂取すると、実際には汗をかきやすくなります。
チゲ鍋などを食すと皆さんもそうなりますよね。
それは辛味が「からだの外側」を温める働きを有するから。
さらにそのうちの何人かは汗をかきます(汗を散らせる)。
漢方の世界では凡そ辛味には散らす働きがあるといわれています。
散らすものには、いろいろ挙なものがあります。
肌の寒気然り、胃腸の湿気然り、筋肉中の痛み然り。
汗をかくというのは、治療の上では風邪をひいた時などに
寒気を散らすための有効な方法とされています。
薬用人参の「温める」という働きは、これらと少し違います。
それは「温める」のと「温まる」の違い。
言葉遊びのように聞こえるかもしれませんが、
温めるというのは外からの温める力、(例えば辛味)が温めるのに対して、
温まるというのは自らを温める力だけが働いている。いわば自活しているわけです。
自らを温める力というのは恒温動物なら誰でも持っているもの。
薬用人参はそういう地力を養うわけです。
すなわち摂取したからだが自らを鼓舞して、自らを温めようとする。
そういう自らの働きですから、
自然というか、身の丈に合っているというか、無理がないというか。
薬用人参が不老長寿の薬と呼ばれる由縁には、
そういうことも関係しているのではないでしょうか。(つづく)
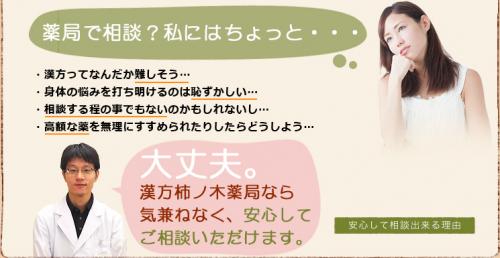
こちらの記事は、漢方柿ノ木薬局のfacebookでも掲載しています。
facebookへはこちらから
また漢方柿ノ木薬局の詳しい情報はこちらでも

















