さまざまな薬用植物をまとめた古書、神農本草経には
薬用人参について次のような記載があります。
味甘微寒。・・・(中略)・・・精神を安んじ、魂魄を定め、驚悸を止め、
・・・(中略)・・・心を開き、智を益して、気を主る。
薬用人参について次のような記載があります。
味甘微寒。・・・(中略)・・・精神を安んじ、魂魄を定め、驚悸を止め、
・・・(中略)・・・心を開き、智を益して、気を主る。

精神や魂魄、心、智などいわゆる無形のものを整えるのも、
人参の薬能の一つとされ、その働きは養心安神と呼ばれます。
人参の薬能の一つとされ、その働きは養心安神と呼ばれます。
漢方では、「気を患うことで、精神は乱れ病む」という点から、
精神や心の不調は、気症(気の道症)と呼ばれます。
現代でいえば、種々の神経症や更年期障害、自律神経失調症、
また原因が不明瞭な不定愁訴も、この気症に該当します。
精神や心の不調は、気症(気の道症)と呼ばれます。
現代でいえば、種々の神経症や更年期障害、自律神経失調症、
また原因が不明瞭な不定愁訴も、この気症に該当します。
漢方では精神や心など目に見えないものは、身体の機能に宿ると考えます。
俗にいう心に宿るのではなく、身体の機能に宿るというところがミソです。
そして身体の機能が乱れると、それに宿る精神も乱れてしまう。
人参には身体の機能を整えて、そこに宿る精神を安定する働きがあります。
俗にいう心に宿るのではなく、身体の機能に宿るというところがミソです。
そして身体の機能が乱れると、それに宿る精神も乱れてしまう。
人参には身体の機能を整えて、そこに宿る精神を安定する働きがあります。
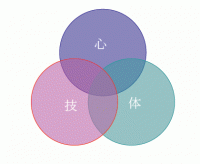
ちなみに漢方では、身体の機能は内臓が発揮すると考えます。
内臓が身体の機能を発揮する。その身体の機能に精神が宿る。
そうして身体の機能を介して、内臓と精神がつながる。
之もまた、漢方独特の考え方です。
前回の薬用人参をお勧めする理由(4) でも紹介しましたが、
でも紹介しましたが、
人参は「中」を整える漢方処方に用いられます。
身体の機能にとっての中心は、それに宿る精神にとっても同じく中心的存在です。
精神的不調に処方される漢方薬に人参が
欠かせないのには、そういう背景があります。
内臓が身体の機能を発揮する。その身体の機能に精神が宿る。
そうして身体の機能を介して、内臓と精神がつながる。
之もまた、漢方独特の考え方です。
前回の薬用人参をお勧めする理由(4)
人参は「中」を整える漢方処方に用いられます。
身体の機能にとっての中心は、それに宿る精神にとっても同じく中心的存在です。
精神的不調に処方される漢方薬に人参が
欠かせないのには、そういう背景があります。

















