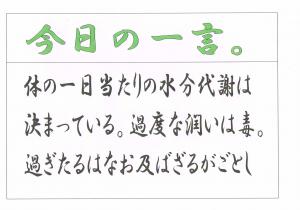
前回に続いて、からだを潤す水について。
漢方ではからだをすみずみまで潤す物質を水=津液と呼び、
飲水で体内へ供給され、汗や尿などで体外へ放出されます。
この『給水』と『排水』のバランスが保たれることで体の潤いは維持されますが
何らかの原因によって、水の貯留や排泄に異常が生じた場合
過度な潤いは毒(水毒)に変わってしまいます。
まさしく『過ぎたるはなお及ばざるがごとし』
水の貯留異常とは
全身を巡る水が何らかの原因によって滞ってしまう状態。
代表的な症状にはむくみ(水滞)があります。
このむくみが
肌や筋肉で生じれば、むくみや水太り、倦怠感となって現れ
関節で生じれば、痛みとなって現れ
大腸内で生じれば、下痢となり、
内耳で生じれば、めまいや耳鳴りを引き起こし
頭部の血管や神経周辺で生じれば、頭痛となり
そして鼻周辺で起これば、鼻水や鼻炎となる。
原因は一重に『水滞』ですが、
それが生じる部位によって症状はかくも多様化してしまいます。
そして漢方の興味深いところは
原因が同じであれば(この場合は水滞)、
訴える症状が違えども
処方される漢方は同じ(異病同治)というところです。

















