本日は、前回までの「鬱」にしばしば随伴する「動悸」という症状について。
心という、目には見えないものに及ぶ「鬱」と
心臓という目に見える器官に及ぶ「動悸」には
やはり密接な関係があると考えられます。
これまで心について、長期にわたり、いささか取り留めもなく論じてきましたが、
その中でもとりわけ
「心が萎(しぼ)む」というのは、「動悸」と結びつけて考えやすいと思います。
すなわち、いろいろなことが影響して、心(こころ)が小さくなると、
身体の心臓の方も働きが鈍くなりやすい。
実際の大きさ(体積)は変わりませんが働きが鈍くなる。
これは見かけ上では心臓が小さくなっている(=狭心)ことと同意です。
然るに、バランスを保とうとして拍動が強くなったり、速くなったりする。
また、そのような心が萎む経緯には
①心に正気(新鮮な気)が注がれない
②心に蓄えられた正気が抜けやすい
という二通りがあるという事も述べましたが、
いずれの場合でも、結果として心に邪気や濁気が満ちやすくなります。
すると先ほどと同様に、身体の心臓にも邪気や濁気が溜まり易くなる。
心臓は循環系の要(かなめ)ですから、
この場合は循環系に邪気や濁気が停滞して、その働きが衰えることにつながります。
つまり、循環が弱まることで血流が弱まり、
血色が悪くなったり、貧血様症状に陥ったり、
むくみが生じることでめまいや乏尿になりやすくなる。
また正気の取り入れ、さらに邪気の排出には呼吸が深く関わっていますから、
この点では動悸と息切れも、「正気の欠乏」でリンクすると考えられます。
動悸時に用いる薬を「気つけ薬」と呼ぶのも、こういう点からなんですよ。
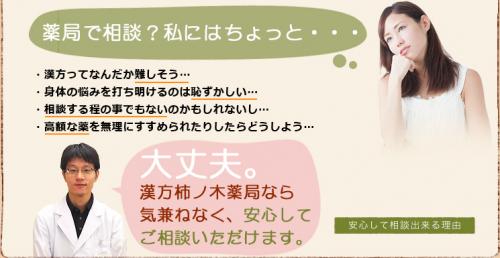
こちらの記事は、漢方柿ノ木薬局のfacebookでも掲載しています。
facebookへはこちらから
また漢方柿ノ木薬局の詳しい情報はこちらでも

















