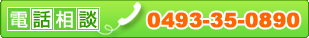冷えは大敵
冷え或は冷え性ほど一般の人からも、また医師からも軽く扱われている病態は無いと思います。
西洋には冷え性と言う病気は無いと言われていますが、本当でしょうか。
それはともかくとして、冷えほど多彩な病気を引き起こしています。
またそれを知らずに放置しておくことがいかに恐ろしいことか、その一部を紹介してみましょう。
冷えが原因と考えられる病気を挙げてみると、アレルギー性鼻炎、花粉症、めまい、生理不順、神経痛、リウマチ、関節痛、むくみ、膀胱炎、急性・慢性胃炎、肌荒れ、にきび、不眠症、便秘、下痢、頭痛など様々です。
いやもっと恐ろしいことがあります。
体温が35℃台か、それ以下の人は癌に罹る率が非常に高いのです。
ところで、冷えとはいったいなんでしょう。
西洋医学では「冷え性」と言う言葉は有りません。
しかし、冷え性に悩む人は意外に多いのです。
手足や腰がいつも冷たく感じる状態で、そのため他人より寒がりである場合を一般に「冷え性」といっています。
東洋医学では「冷え性」と「冷え」とは区別しています。
「冷え」とは下半身、特に足首から先が冷たく感じるものを言い、「冷えのぼせ」とも言っています。
ところで「冷え」は男性にも見られますが、特に女性に多くみられます。
冷たい空気は下の方に溜まりやすく、一番冷たい空気の影響を受けるのは足元なのです。
足先は冷えて血行が悪くなり、ますます悪循環となって冷えて行きます。
その冷えは次第に体の上のほうに上がってきて腰から下腹部へと冷えてきます。
しかし手足は動きますので、必然的にある程度、血液循環が強制的に行われますが、下腹部の方はそうはいかず、一度冷えるとなかなか暖まりません。
血行状態の悪くなった状態を瘀血(おけつ)(ふる血)といいます。
女性は男性と比べ下腹部の内臓が多く(子宮)、構造が複雑で、瘀血がたまりやすいのです。
もう一つ、特に若い女性はファッションに敏感で下半身の冷えやすい衣服(ミニスカートなど)を着ていることにも大きな原因があります。
日本の冬は冷えやすいので、昔の日本人は着物を着ていました。
冬はスカートよりもスラックスを着用したほうが健康にはいいですね。
以上のように、冷えると血液循環が悪く内臓の働きが低下して、老廃物や炭酸ガスがたまって異常な働きをするようになると思われます。
それが体のいろんなところに思いも寄らぬ症状を起こすのではないかと思われます。
人それぞれに起こる症状は異なっても、原因はみんな「冷え」なのです。
体が冷えると細胞への血液の供給が充分に行われず、必要な酸素や栄養物が不足し、不必要なものがたまって来ます。
すると細胞の働きは低下し、いろいろな変化を来たすようになります。
冷えの対策には、衣類や住まいの環境の改善と共に、食事の注意が大切です。
冬は生野菜、果物、生もの、冷たい飲料水を控えて、火を通して食べること、砂糖より塩分を多く取ることが大切です。
東洋医学には西洋医学には無い考え方があります。
使用する薬物を温める働きのあるものと冷やす働きのあるものに区別していることです。
西洋薬は大半が体を冷やす性質を持っていて、味も苦いものがほとんどです。
反面、漢方薬は「性味(せいみ)」と言って、性質には体を温めるものから冷やすものまで五種類(熱(ねつ)、温(おん)、平(へい)、涼(りょう)、寒(かん))があり、味も五種類(酸(すっぱい)、苦(にがい)、甘(あまい)、辛(からい)、鹹(しょっぱい))あります。
冷えに対して使用する漢方薬も、全身的な冷えに対するもの、下半身の冷えに対するもの、腹部の冷えに対するもの、冷えのぼせに対するもの、瘀血を積極的に循環させるためなど、それぞれの病態に応じて、数え切れないほどの漢方薬を使い分けます。
漢方薬の効果は良く状態を見極め、適当な薬方を使用したときは、驚くほどの効果を見ることが多々あります。
漢方薬といえば、長く内服するものと思っている人が多いようですが、一服あるいは数日の服用で症状を改善してしまう例のあることを一般の人はご存知無いようです。
現在、日本では二人に一人は癌に罹るといわれていますが、戦後急速に変化した日本の食事も原因の一つかと案じています。
癌も冷えからとの報告もありますので、冷えぐらいとほっておくわけにはいけませんね。
惠木 弘・著 『冬こそ若返る! 四季の養生法』より