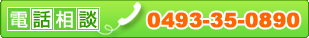自然界は、秋になると木々は実をつけ、動物は栄養をとり、冬に向けての準備を始めます。
素問に書かれている秋の養生法には、「秋は万物が実を結ぶ時だ。すべてが引き締まり、収納される時期である。当然陽気も体内深く収納される。この時期は早く寝て鶏と共に起きる。あれもやりたいこれもやりたいなど、イライラして活動的になってはいけない。この時期に活動しすぎて、陽気を発散する(汗をかきすぎること)と、肺が弱り、冬になって下痢をするようになる」と書かれています。
自然界を五つに分けて考えた「五行論」では、秋に相当する五臓は肺で、大腸・鼻・皮膚がこれに関与しています。
汗をかきすぎると風邪をひきやすいことは皆さまも経験されたことがあると思います。
秋といえば、「スポーツの秋」といってスポーツが盛んになりますが、「過ぎたるは及ばざるが如し」で、自分の体力に合ったスポーツを適度にすることが肝要かと思います。
また、「食欲の秋」「天高く馬肥ゆる秋」ともいい、グルメを楽しむ季節とも言えるでしょう。
中医学では、私たちが食べたものや飲んだ水分は「脾(五臓の一つで、西洋医学での胃腸に相当)」の働きで消化吸収されて、「肺」に運ばれ、肺は自然の空気(清気という)を取り入れ、飲食物から吸収した栄養物(穀気という)と合わせて、気血津液に変えて、体全体に行き渡らせます(中医学で肺の宣散・粛降作用と言っています)。
また、肺は皮毛(皮膚・汗腺・うぶ毛)に栄養物(衛気という)を送り、外界から体を守る働き(免疫作用)があります。
汗の調節も肺の働きの一つと考えています。
東洋医学では衛気の働きを強める作用を持つ黄耆という生薬を免疫強化の目的で使用し、易感冒、皮膚疾患(特にアトピー等)、癌などに応用しています。
肺は気管支・気管・咽頭を通じて鼻につながっています。
このことを中医学では「肺は鼻に開窮する」と言って、鼻の病気も肺との関連を考え、また難治性の疾患では肺の奥の「脾(胃腸)」との関連も考えて治療いたします。
肺の働きに異常があると便秘や下痢が現れることもあります。
以上のように、中医学では人体を相互関連のものとしてとらえ、相互不可分という考えが基本になっています。
この様に、私達の体を部分的にとらえないで、からだ全体の調和を整える事を大切にする医学が、老後の健康を増進することに大きく貢献いたします。
解説:惠木 弘(恵心堂漢方研究所所長)