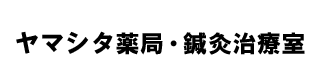今年は猛暑・残暑に続いて、秋になってもなかなか気候が落ち着いてくれませんね。
こんな時は「胃腸の不調」を訴える方が多く来られます。
さて私、昨日台風26号接近のニュースを横目に地元の研修会「消化器疾患の診断と治療のポイント」に行ってまいりました。
内容的には予想通り(良い意味で)でしたが、最近の新しい考え方「機能性疾患」についての講演は興味深いものでした。
つまり消化器疾患を「悪性(ガンなど)」と「良性」に分け、「良性」を”器質性”(臓器に病変があるもの)と”機能性”(臓器に病変が無いもの)に分けて考えるのです。
この中で気になったのは「良性」の”機能性”疾患です。
消化器は大きく①食道②胃③腸に分かれていますが、それぞれの部位で「良性」の”機能性”疾患があるのです。
例えば、①食道では「逆流性食道炎」のうちごく初期のもの(非びらん性胃食道炎)、②胃では「機能性ディスペプシア」、③腸では「過敏性腸症候群」が当てはまります。
「機能性ディスペプシア」の定義は、”特に原因が無く、胃のもたれ、膨満感、胸やけ、胃の痛みがあるもの”です。
また「過敏性腸症候群」についても”器質的な病変が無く、下痢・軟便、便秘を繰り返すもの”とされています。
これらの疾患に共通しているのは、これと言った原因が特定できず、個々の体質に加えてストレスによって誘発されることです。治療は対症療法で行われるようですが、お医者さんにとっても「治した!」「治った!!」という実感が無く、言い方は悪いですが「気合の入らない」疾患のようです。患者さんが焦れてしまって、いわゆる「ドクターショッピング」が多いのも特徴です。
そのために、これまで病院に行っても「気のせい」とか「安静にしていればそのうち」と言われ、薬物療法にも決め手が無く「消化剤と整腸剤しか出してくれない」「全然治らない」と来店される方もおられます。
しかしまあ、こんな症状こそ漢方の出番です。
この夏もこういうお客さんが何人かいましたが、何とか”食欲の秋”を迎えることができました。
昔からこれらの胃腸症状は人びとを苦しめてきたのです。
これまで数千年に亘って「漢方薬」が愛され、飲み続けられて来たのは、これらの症状を一つも切り捨てること無く、決して「気のせい」にせず真摯に向き合ってきたからでしょう。
皆さんの症状に合う漢方薬は必ずあります。
ご相談ください。
| ツイート |
|
更新日: 2013/10/16 |